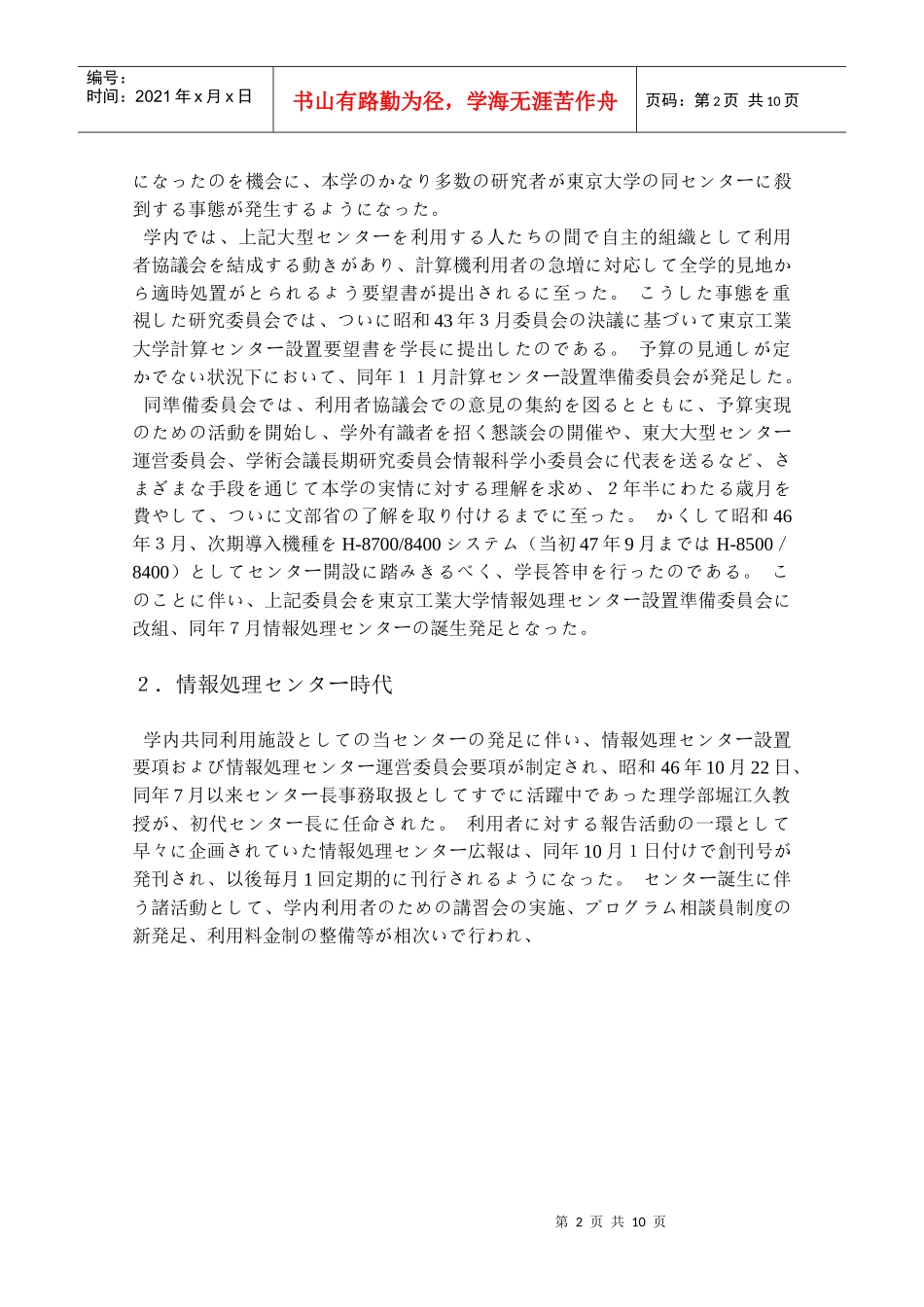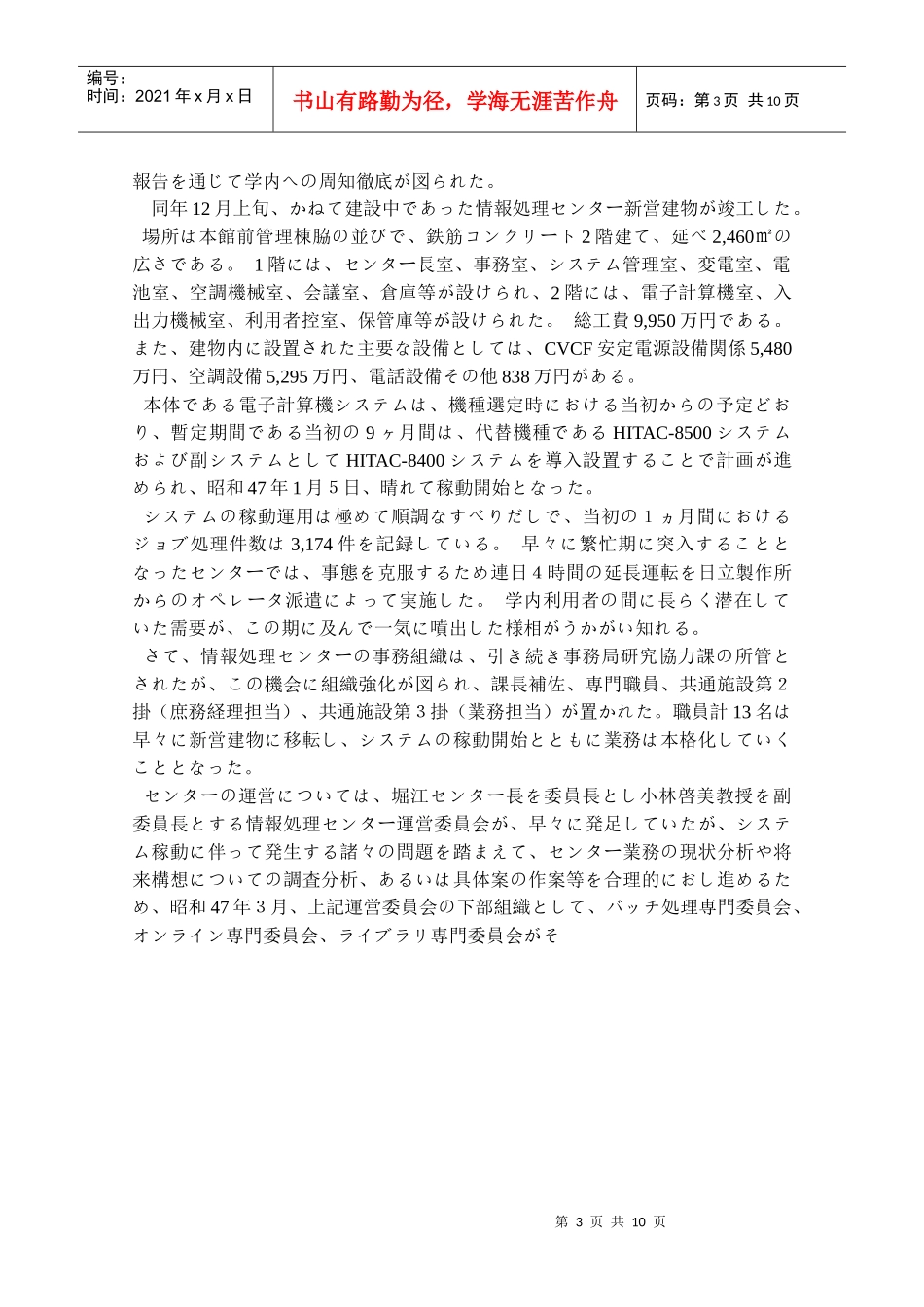第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页1.共通研究施設電子計算機室時代電子計算機が戦後世に現れ目覚しい躍進を遂げる中で、技術革新時代の基盤を大きく支え、学問技術の諸分野に絶大な貢献を果たし続けてきた実績は、衆目の認めるところである。本邦における計算機産業がようやく起動に乗り始め、各界における計算機利用が華々しく展開され始めた昭和35年頃、本学でもこれに関心を寄せ、研究上への計算機利用をもくろむ人たちが現れるようになった。そうした中で、共通研究施設電子計算機室が設置された。時は昭和38年4月1日である。この計算機室は事務局研究協力課所管とされ、同年3月末導入された電算機FACOM-222(買取価格8,500万円)を本館地下38号室に設置して、業務が開始された。37号室がMG用、16号室が保守室用に割り当てられ、専任技官2名、技術補佐員2名による保守管理に支えられて、運用が始まったのである。管理運営に関しては、電子計算機管理委員会が組織され、同年9月には東京工業大学計算機室使用内規が制定施行されるなど、ようやく運営は軌道に乗っていった。機器構成としては、FACOM-222を本体とし、内部記憶装置4kW、外部記憶に磁気テープ装置2台、これに紙テープ入力装置とLP出力装置から成るシステムとして出発したが、暫時借り入れ等により、FACOM-322、内部記憶容量4kWの追加、磁気ドラム装置10kW、カード入出力装置MT3台等の増設が行われていった。ちなみに、昭和43年度におけるジョブ処理件数は4,602件で、機械工学系を筆頭に原子炉研、土木建築系と続いて全学に及ぶ約200名の利用者があった。計算機室開設以来、利用者の便宜を図るためオープンショップ方式の採用やセミクローズ方式の併用など種々運用上の改善努力が重ねられたが、逐年増加し始めるようになった利用者の要望を受け入れるには、計算機システムの能力(乗算速度0.8ms)は余りにも低いものであった。学外では昭和41年以来全国共同利用大型計算機センターが逐次稼動を開始すること第2页共10页第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共10页になったのを機会に、本学のかなり多数の研究者が東京大学の同センターに殺到する事態が発生するようになった。学内では、上記大型センターを利用する人たちの間で自主的組織として利用者協議会を結成する動きがあり、計算機利用者の急増に対応して全学的見地から適時処置がとられるよう要望書が提出されるに至った。こうした事態を重視した研究委員会では、ついに昭和43年3月委員会の決議に基づいて東京工業大学計算センター設置要望書を学長に提出したのである。予算の見通しが定かでない状況下において、同年11月計算センター設置準備委員会が発足した。同準備委員会では、利用者協議会での意見の集約を図るとともに、予算実現のための活動を開始し、学外有識者を招く懇談会の開催や、東大大型センター運営委員会、学術会議長期研究委員会情報科学小委員会に代表を送るなど、さまざまな手段を通じて本学の実情に対する理解を求め、2年半にわたる歳月を費やして、ついに文部省の了解を取り付けるまでに至った。かくして昭和46年3月、次期導入機種をH-8700/8400システム(当初47年9月まではH-8500/8400)としてセンター開設に踏みきるべく、学長答申を行ったのである。このことに伴い、上記委員会を東京工業大学情報処理センター設置準備委員会に改組、同年7月情報処理センターの誕生発足となった。2.情報処理センター時代学内共同利用施設としての当センターの発足に伴い、情報処理センター設置要項および情報処理センター運営委員会要項が制定され、昭和46年10月22日、同年7月以来センター長事務取扱としてすでに活躍中であった理学部堀江久教授が、初代センター長に任命された。利用者に対する報告活動の一環として早々に企画されていた情報処理センター広報は、同年10月1日付けで創刊号が発刊され、以後毎月1回定期的に刊行...