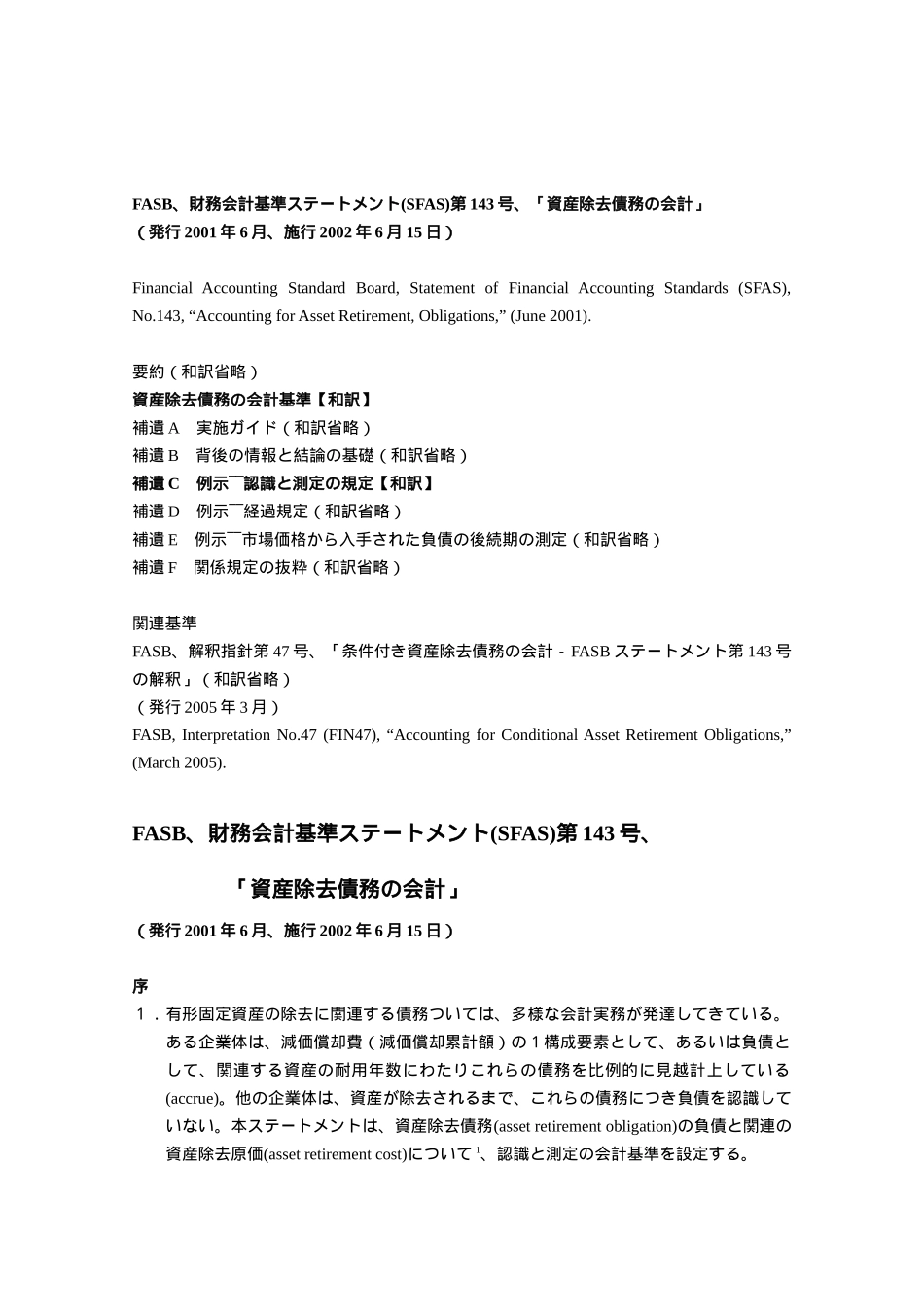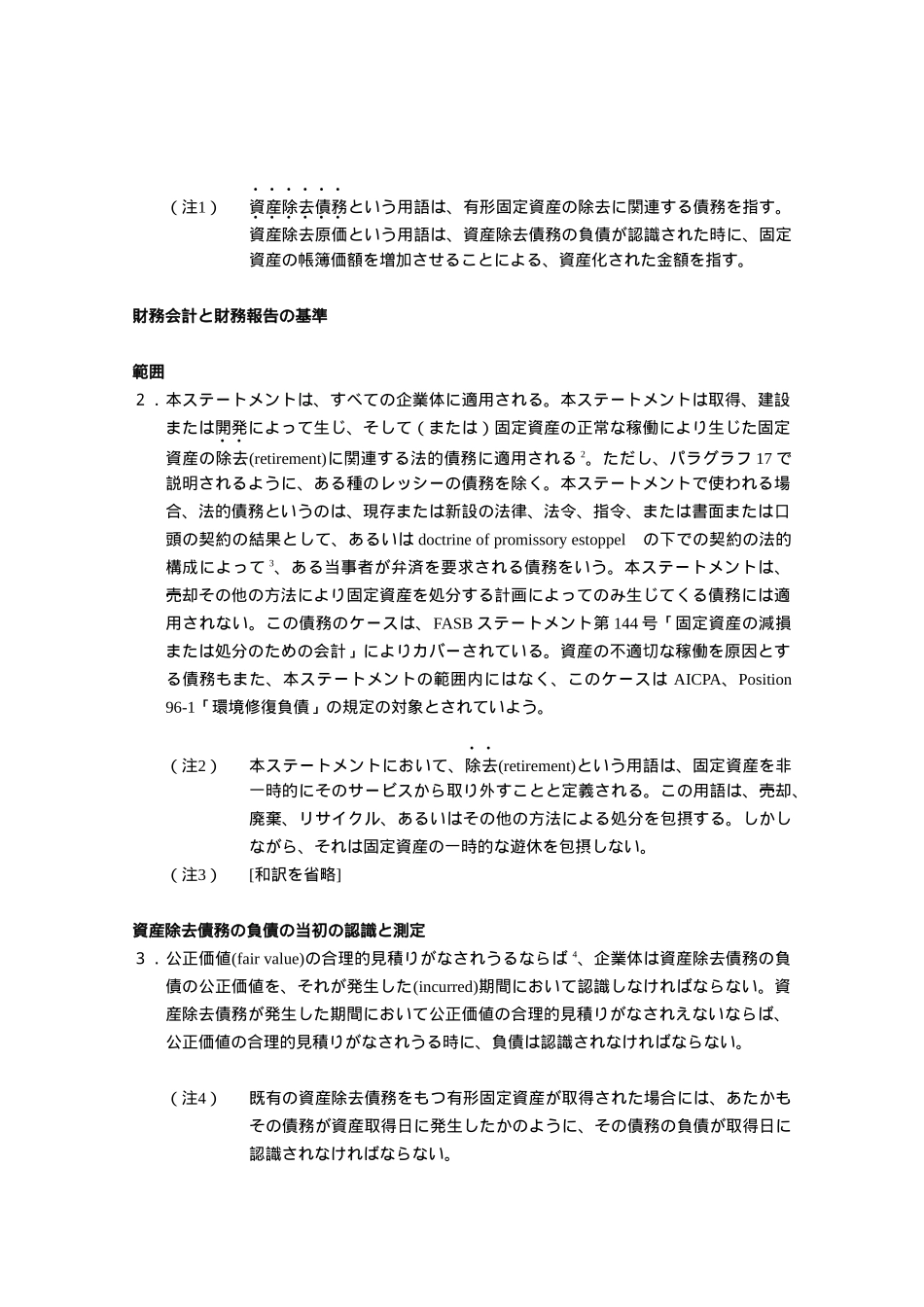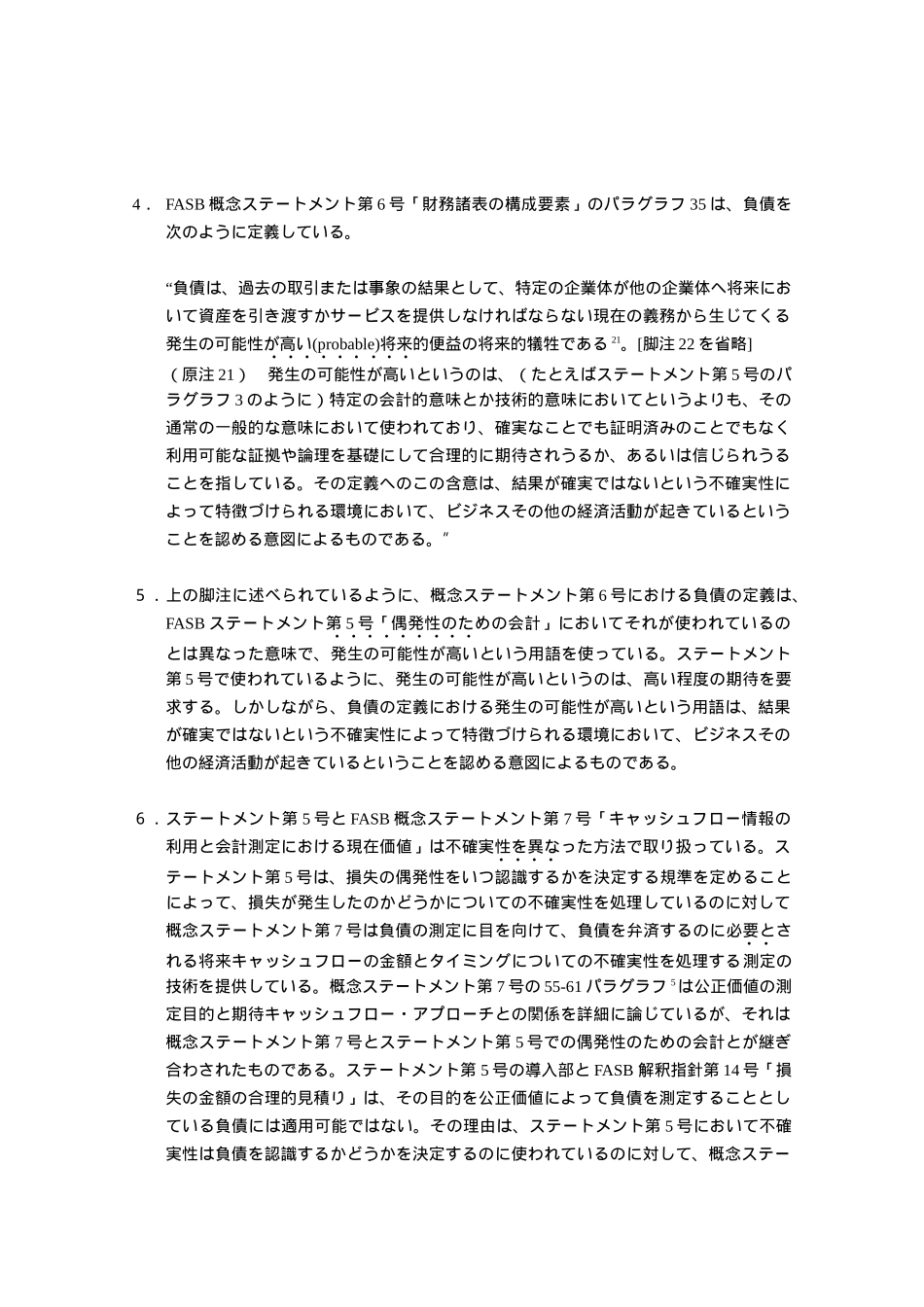FASB、財務会計基準ステートメント(SFAS)第143号、「資産除去債務の会計」(発行2001年6月、施行2002年6月15日)FinancialAccountingStandardBoard,StatementofFinancialAccountingStandards(SFAS),No.143,“AccountingforAssetRetirement,Obligations,”(June2001).要約(和訳省略)資産除去債務の会計基準【和訳】補遺A実施ガイド(和訳省略)補遺B背後の情報と結論の基礎(和訳省略)補遺C例示認識と測定の規定【和訳】――補遺D例示経過規定(和訳省略)――補遺E例示市場価格から入手された負債の後続期の測定(和訳省略)――補遺F関係規定の抜粋(和訳省略)関連基準FASB、解釈指針第47号、「条件付き資産除去債務の会計-FASBステートメント第143号の解釈」(和訳省略)(発行2005年3月)FASB,InterpretationNo.47(FIN47),“AccountingforConditionalAssetRetirementObligations,”(March2005).FASB、財務会計基準ステートメント(SFAS)第143号、「資産除去債務の会計」(発行2001年6月、施行2002年6月15日)序1.有形固定資産の除去に関連する債務ついては、多様な会計実務が発達してきている。ある企業体は、減価償却費(減価償却累計額)の1構成要素として、あるいは負債として、関連する資産の耐用年数にわたりこれらの債務を比例的に見越計上している(accrue)。他の企業体は、資産が除去されるまで、これらの債務につき負債を認識していない。本ステートメントは、資産除去債務(assetretirementobligation)の負債と関連の資産除去原価(assetretirementcost)について1、認識と測定の会計基準を設定する。(注1)資産除去債務という用語は、有形固定資産の除去に関連する債務を指す。資産除去原価という用語は、資産除去債務の負債が認識された時に、固定資産の帳簿価額を増加させることによる、資産化された金額を指す。財務会計と財務報告の基準範囲2.本ステートメントは、すべての企業体に適用される。本ステートメントは取得、建設または開発によって生じ、そして(または)固定資産の正常な稼働により生じた固定資産の除去(retirement)に関連する法的債務に適用される2。ただし、パラグラフ17で説明されるように、ある種のレッシーの債務を除く。本ステートメントで使われる場合、法的債務というのは、現存または新設の法律、法令、指令、または書面または口頭の契約の結果として、あるいはdoctrineofpromissoryestoppelの下での契約の法的構成によって3、ある当事者が弁済を要求される債務をいう。本ステートメントは、売却その他の方法により固定資産を処分する計画によってのみ生じてくる債務には適用されない。この債務のケースは、FASBステートメント第144号「固定資産の減損または処分のための会計」によりカバーされている。資産の不適切な稼働を原因とする債務もまた、本ステートメントの範囲内にはなく、このケースはAICPA、Position96-1「環境修復負債」の規定の対象とされていよう。(注2)本ステートメントにおいて、除去(retirement)という用語は、固定資産を非一時的にそのサービスから取り外すことと定義される。この用語は、売却、廃棄、リサイクル、あるいはその他の方法による処分を包摂する。しかしながら、それは固定資産の一時的な遊休を包摂しない。(注3)[和訳を省略]資産除去債務の負債の当初の認識と測定3.公正価値(fairvalue)の合理的見積りがなされうるならば4、企業体は資産除去債務の負債の公正価値を、それが発生した(incurred)期間において認識しなければならない。資産除去債務が発生した期間において公正価値の合理的見積りがなされえないならば、公正価値の合理的見積りがなされうる時に、負債は認識されなければならない。(注4)既有の資産除去債務をもつ有形固定資産が取得された場合には、あたかもその債務が資産取得日に発生したかのように、その債務の負債が取得日に認識されなければならない。4.FASB概念ステートメント第6号「財務諸表の構成要素」のパラグラフ35は、負債を次のように定義している。“負債は、過...