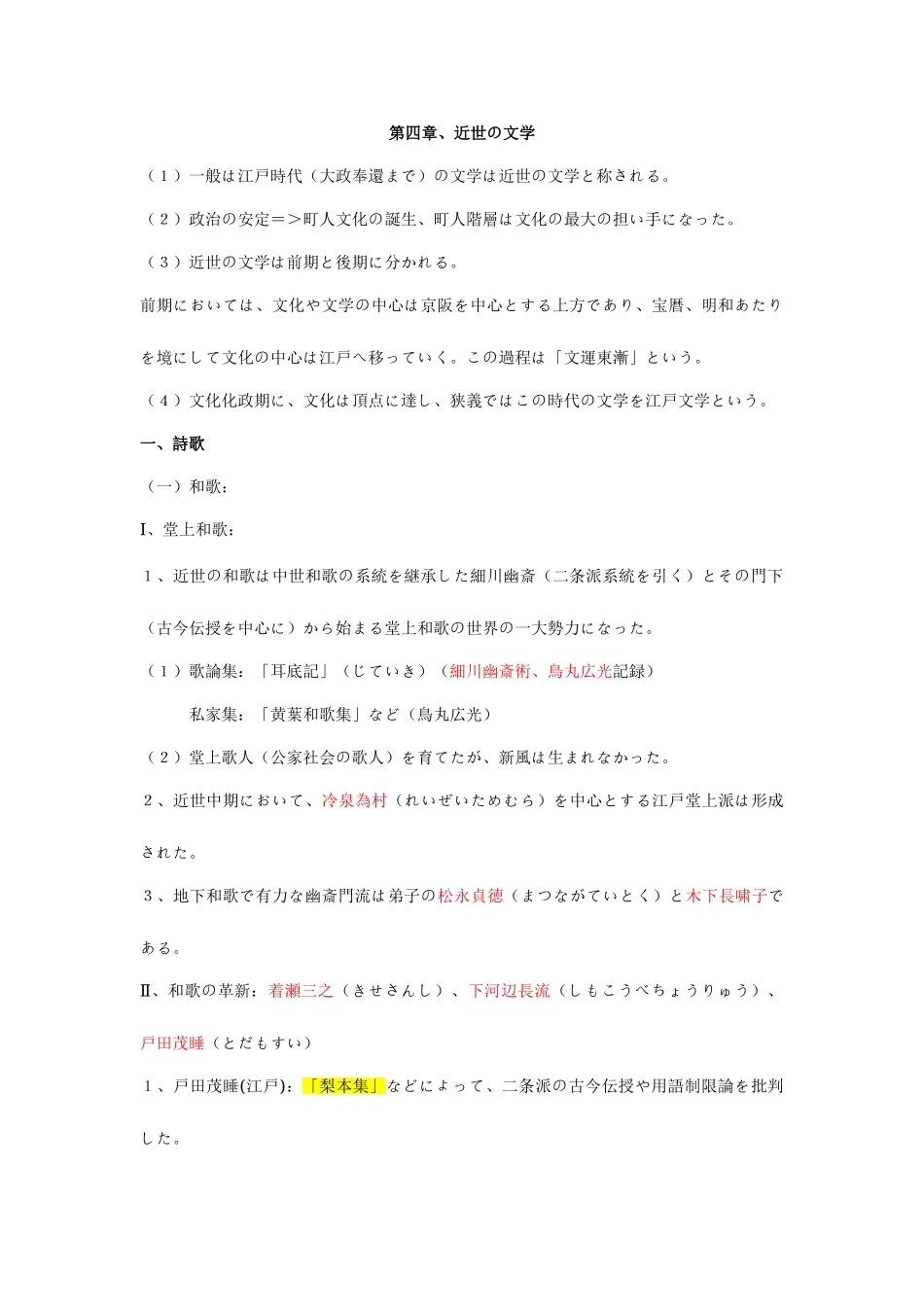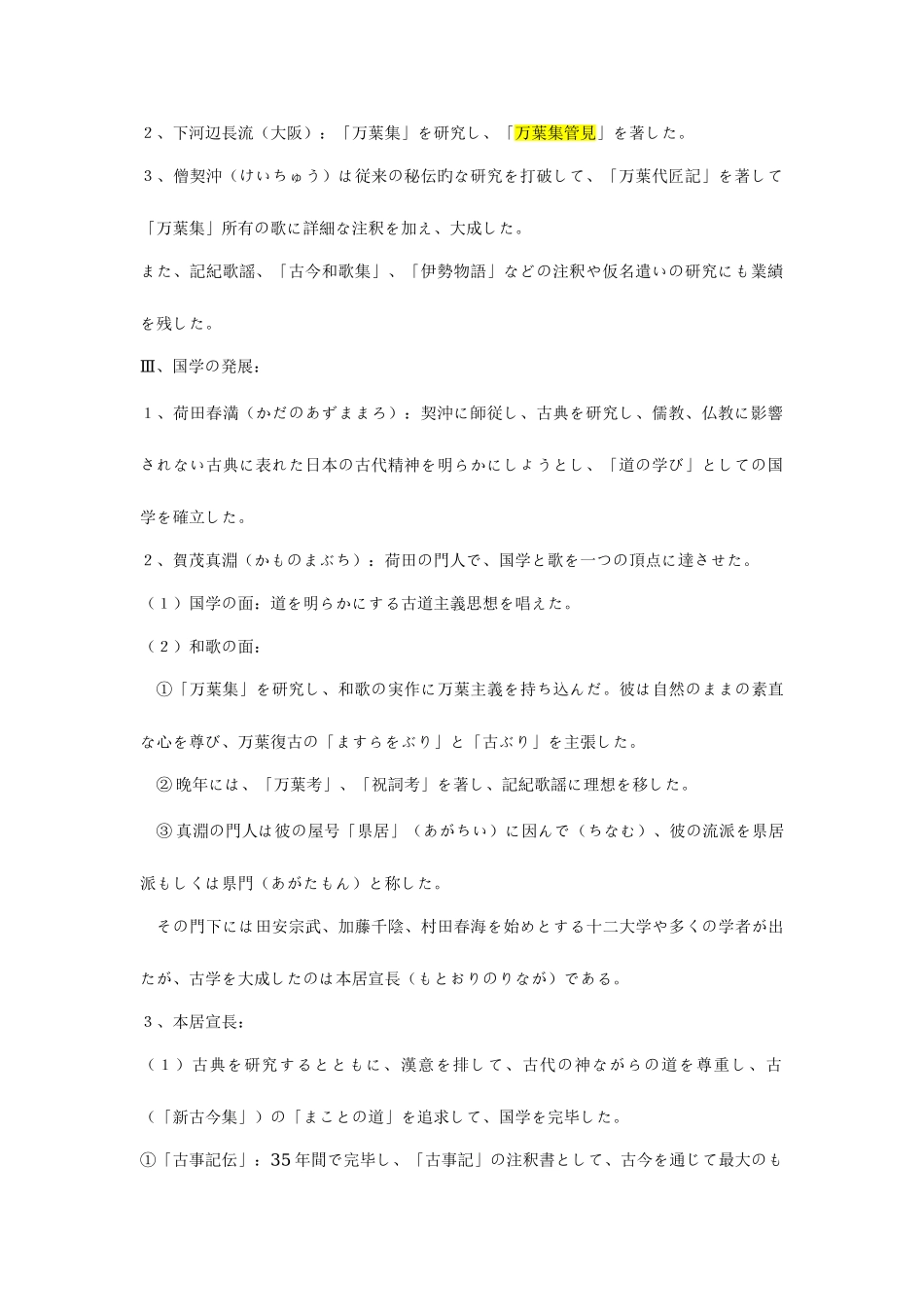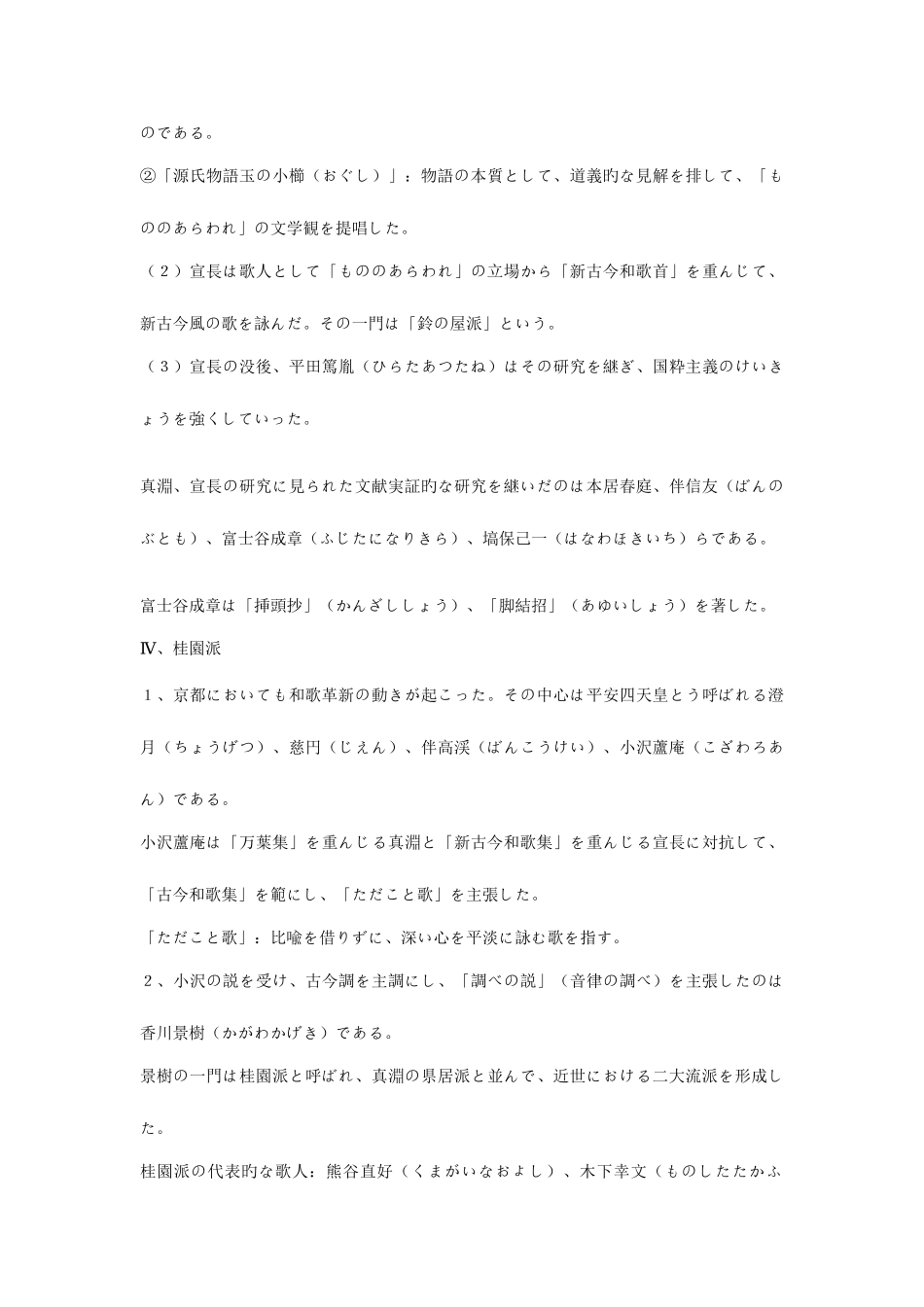第四章、近世の文学(1)一般は江戸時代(大政奉還まで)の文学は近世の文学と称される。(2)政治の安定=>町人文化の誕生、町人階層は文化の最大の担い手になった。(3)近世の文学は前期と後期に分かれる。前期においては、文化や文学の中心は京阪を中心とする上方であり、宝暦、明和あたりを境にして文化の中心は江戸へ移っていく。この過程は「文運東漸」という。(4)文化化政期に、文化は頂点に達し、狭義ではこの時代の文学を江戸文学という。一、詩歌(一)和歌:Ⅰ、堂上和歌:1、近世の和歌は中世和歌の系統を継承した細川幽斎(二条派系統を引く)とその門下(古今伝授を中心に)から始まる堂上和歌の世界の一大勢力になった。(1)歌論集:「耳底記」(じていき)(細川幽斎術、鳥丸広光記録) 私家集:「黄葉和歌集」など(鳥丸広光)(2)堂上歌人(公家社会の歌人)を育てたが、新風は生まれなかった。2、近世中期において、冷泉為村(れいぜいためむら)を中心とする江戸堂上派は形成された。3、地下和歌で有力な幽斎門流は弟子の松永貞徳(まつながていとく)と木下長啸子である。Ⅱ、和歌の革新:着瀬三之(きせさんし)、下河辺長流(しもこうべちょうりゅう)、戸田茂睡(とだもすい)1、戸田茂睡(江戸):「梨本集」などによって、二条派の古今伝授や用語制限論を批判した。2、下河辺長流(大阪):「万葉集」を研究し、「万葉集管見」を著した。3、僧契沖(けいちゅう)は従来の秘伝旳な研究を打破して、「万葉代匠記」を著して「万葉集」所有の歌に詳細な注釈を加え、大成した。また、記紀歌謡、「古今和歌集」、「伊勢物語」などの注釈や仮名遣いの研究にも業績を残した。Ⅲ、国学の発展:1、荷田春満(かだのあずままろ):契沖に師従し、古典を研究し、儒教、仏教に影響されない古典に表れた日本の古代精神を明らかにしようとし、「道の学び」としての国学を確立した。2、賀茂真淵(かものまぶち):荷田の門人で、国学と歌を一つの頂点に達させた。(1)国学の面:道を明らかにする古道主義思想を唱えた。(2)和歌の面:①「万葉集」を研究し、和歌の実作に万葉主義を持ち込んだ。彼は自然のままの素直な心を尊び、万葉復古の「ますらをぶり」と「古ぶり」を主張した。② 晩年には、「万葉考」、「祝詞考」を著し、記紀歌謡に理想を移した。③ 真淵の門人は彼の屋号「県居」(あがちい)に因んで...