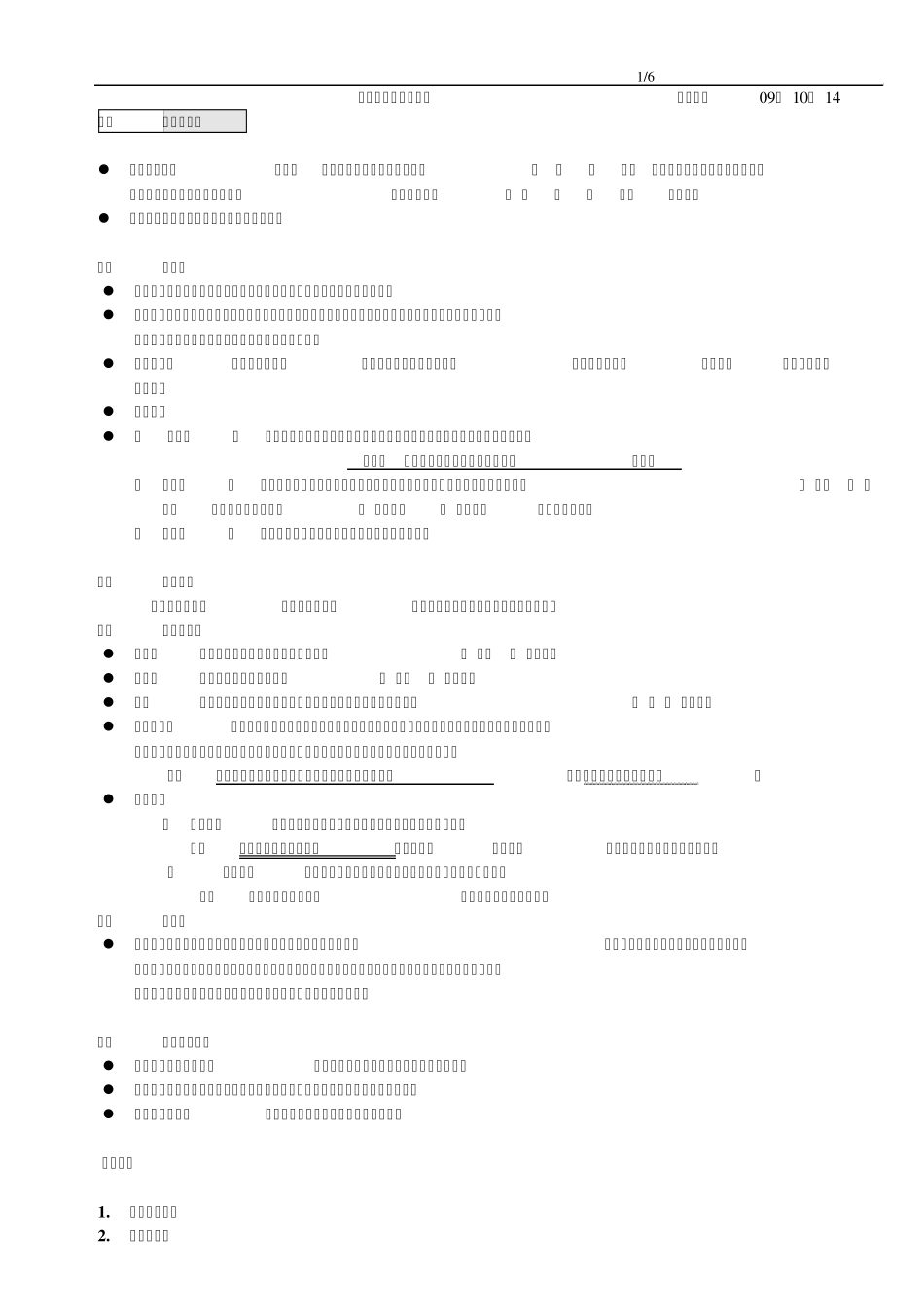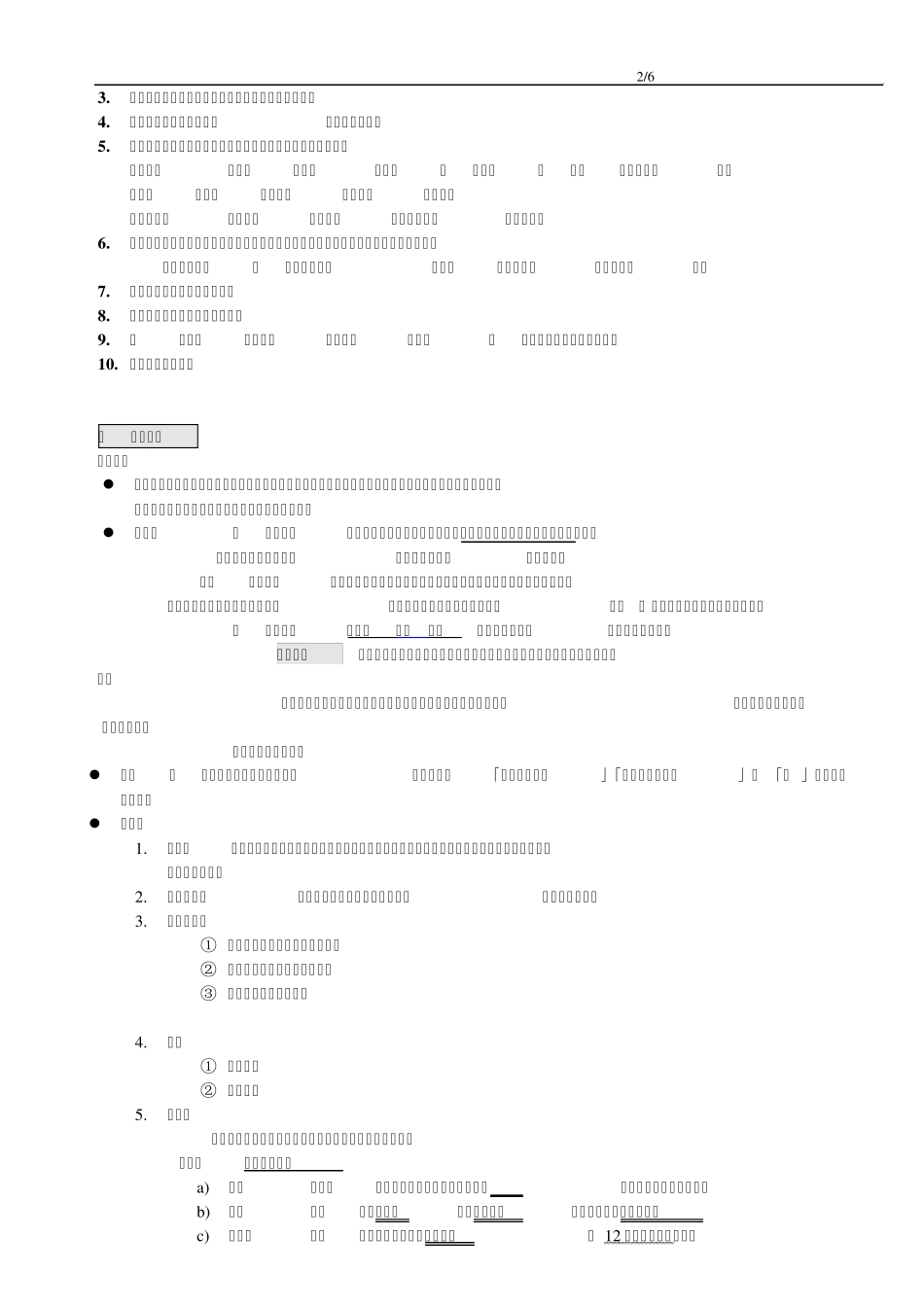1 /6 日本語句法と篇章法 作成日: 0 9 ・ 1 0 ・ 1 4 一、 文と構文論 言語の単位: 形態素(意味を持った最小の音形)→ 語 → 連語(二つ以上の単語が一つづきになって複合した観念を表すもの 【節】を含む ) → 文 → 文章 (談話) 文は言語表現の最も基本的な単位である。 二、 語とは 文を構成する単位の中で最も基本なものは語(単語ともいう)である。 【品詞】語は文を作るための最も重要な材料であり、文を組みたてる上一定の働きをする。この職能の違いによって語を種類区別したものが品詞である。 品詞種類: 名詞、代名詞、 動詞、形容詞、形容動詞、 連体詞、副詞、 接続詞、 感動詞、助動詞、助詞 語の構造 ① 活用語 : 文中での働きの違いに応じて形を変える語、即ち、語形変化する語をいう 用言:(動詞·形容詞·形容動詞)& 助動詞 ② 派生語 : ある語に付加的要素がついてできる語を派生語という。この付加的要素を「 接辞」 という 派生語の中心要素を「 派生語幹」 という。 接頭辞と接尾辞 ③ 複合語 : 複数の語が結合して一語となったものをいう。 三、 文の特徴 形態の独立体、 構造の統一体、 意味の完結体(文の重要な特徴である) 四、 単文と複文 単文: 単一の述語を中心に構成された文を「 単文」 という。 複文: 複数の述語からなる文を「 複文」 という。 節: 複文を構成するところの、述語を中心とした各まとまりを、「 節 」 と呼ぶ。 〖主節〗: 複文は複数の節で構成されるが、それらの中で、原則として、文末n述語を中心とした節が文全体を纏まる働きをする。これは主節という。主節以外の節は、〖接続節〗と呼ぶ。 例: 王さんが重い荷物を軽々と運んだので(接続節)、趙さんは驚いた(主節)。 接続節: ① 従属節: 主節にたいして従属的な関係で結びつくものをいう。 例: 春になると(従属節)、花が咲く (主節) 君が行くなら、僕はいかない。 ② 並列節: 主節に対して、対等の並ぶ関係で結びつくものをいう。 例: 山は高く、水は深い 花も美しいし、香もよい 五、 構文論 語を扱う文法を形態論といい、文を扱う文法を構文論という。 構文論(統語論·統辞論·シンタクスともいう)は文を構成する要素の配列様式と、その機能...