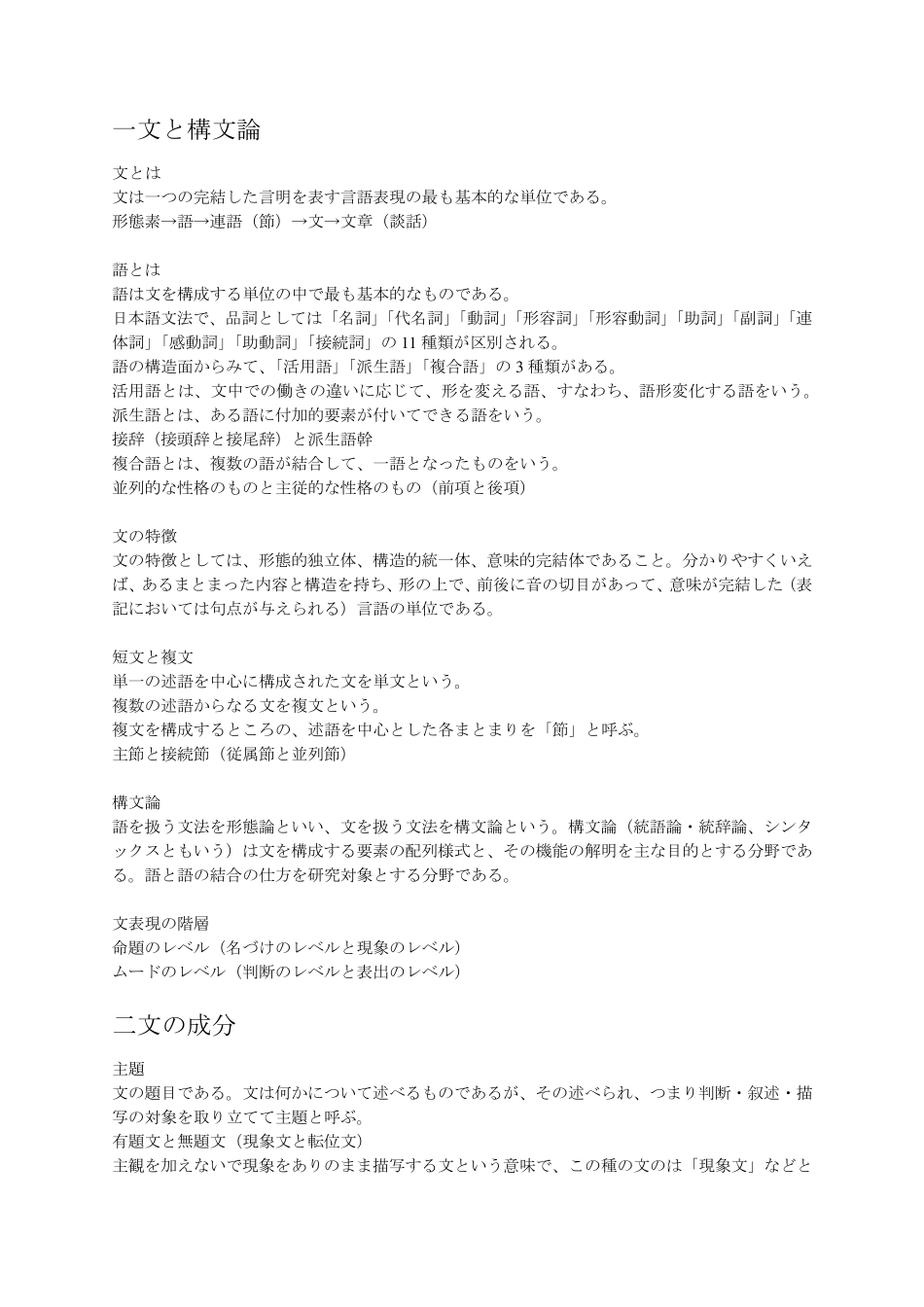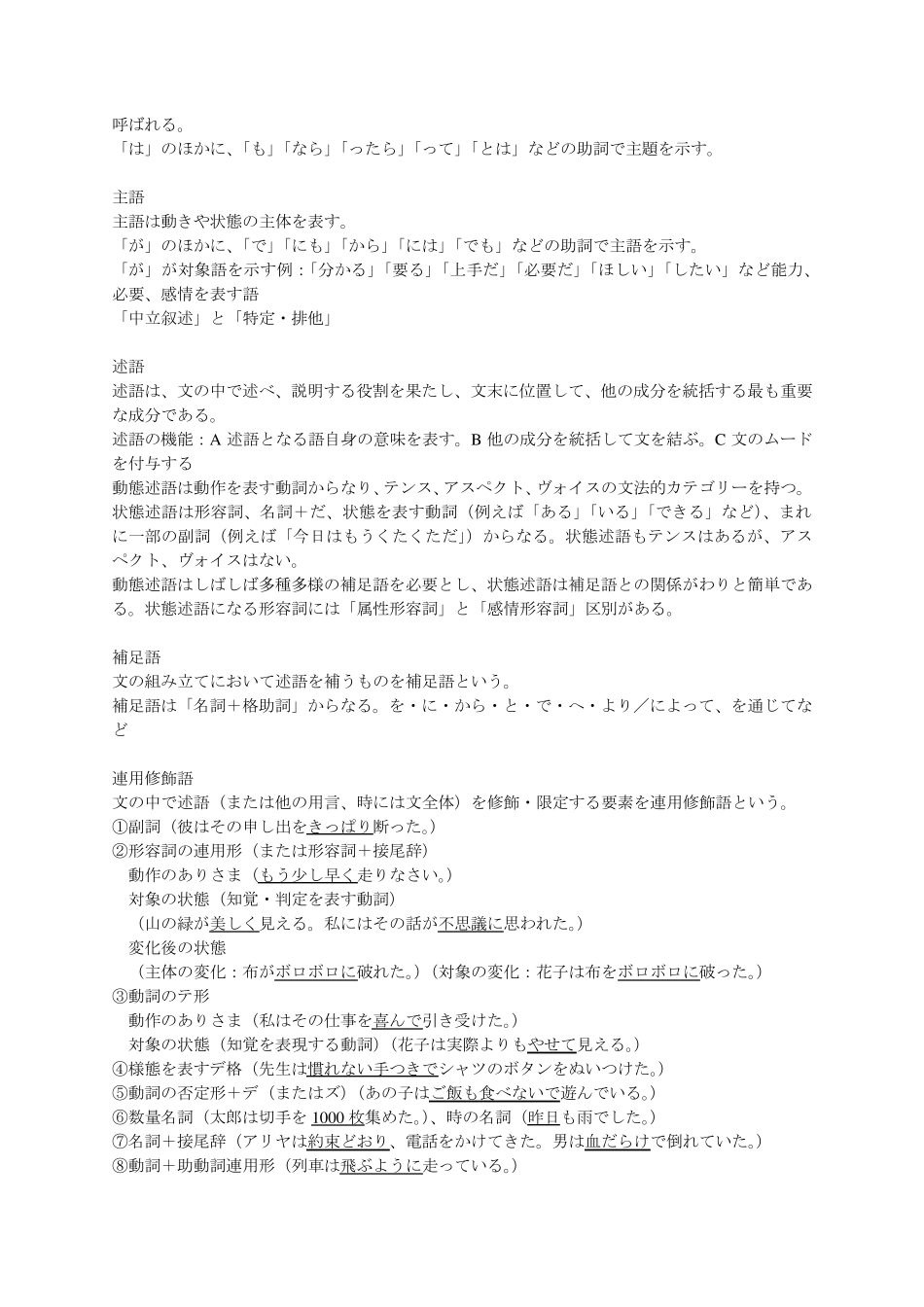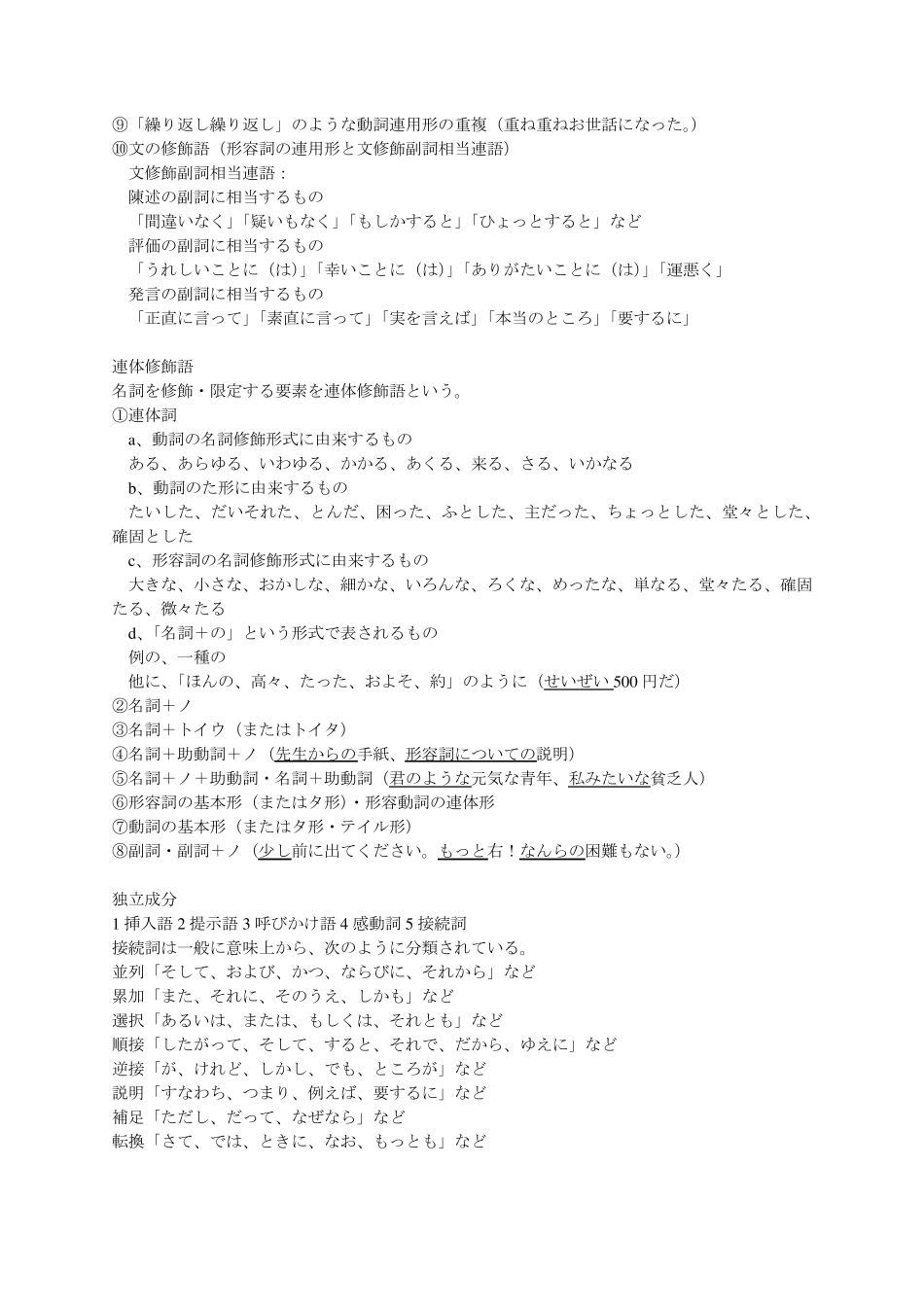一文と構文論 文とは 文は一つの完結した言明を表す言語表現の最も基本的な単位である。 形態素→語→連語(節)→文→文章(談話) 語とは 語は文を構成する単位の中で最も基本的なものである。 日本語文法で、品詞としては「名詞」「代名詞」「動詞」「形容詞」「形容動詞」「助詞」「副詞」「連体詞」「感動詞」「助動詞」「接続詞」の1 1 種類が区別される。 語の構造面からみて、「活用語」「派生語」「複合語」の3 種類がある。 活用語とは、文中での働きの違いに応じて、形を変える語、すなわち、語形変化する語をいう。 派生語とは、ある語に付加的要素が付いてできる語をいう。 接辞(接頭辞と接尾辞)と派生語幹 複合語とは、複数の語が結合して、一語となったものをいう。 並列的な性格のものと主従的な性格のもの(前項と後項) 文の特徴 文の特徴としては、形態的独立体、構造的統一体、意味的完結体であること。分かりやすくいえば、あるまとまった内容と構造を持ち、形の上で、前後に音の切目があって、意味が完結した(表記においては句点が与えられる)言語の単位である。 短文と複文 単一の述語を中心に構成された文を単文という。 複数の述語からなる文を複文という。 複文を構成するところの、述語を中心とした各まとまりを「節」と呼ぶ。 主節と接続節(従属節と並列節) 構文論 語を扱う文法を形態論といい、文を扱う文法を構文論という。構文論(統語論・統辞論、シンタックスともいう)は文を構成する要素の配列様式と、その機能の解明を主な目的とする分野である。語と語の結合の仕方を研究対象とする分野である。 文表現の階層 命題のレベル(名づけのレベルと現象のレベル) ムードのレベル(判断のレベルと表出のレベル) 二文の成分 主題 文の題目である。文は何かについて述べるものであるが、その述べられ、つまり判断・叙述・描写の対象を取り立てて主題と呼ぶ。 有題文と無題文(現象文と転位文) 主観を加えないで現象をありのまま描写する文という意味で、この種の文のは「現象文」などと呼ばれる。 「は」のほかに、 「も」 「なら」 「ったら」 「って」 「とは」などの助詞で主題を示す。 主語 主語は動きや状態の主体を表す。 「が」のほかに、 「で」 「にも」 「から」 「には」 「でも」などの助詞で主語を示す。 「が」が対象語を示す例: 「分かる」...