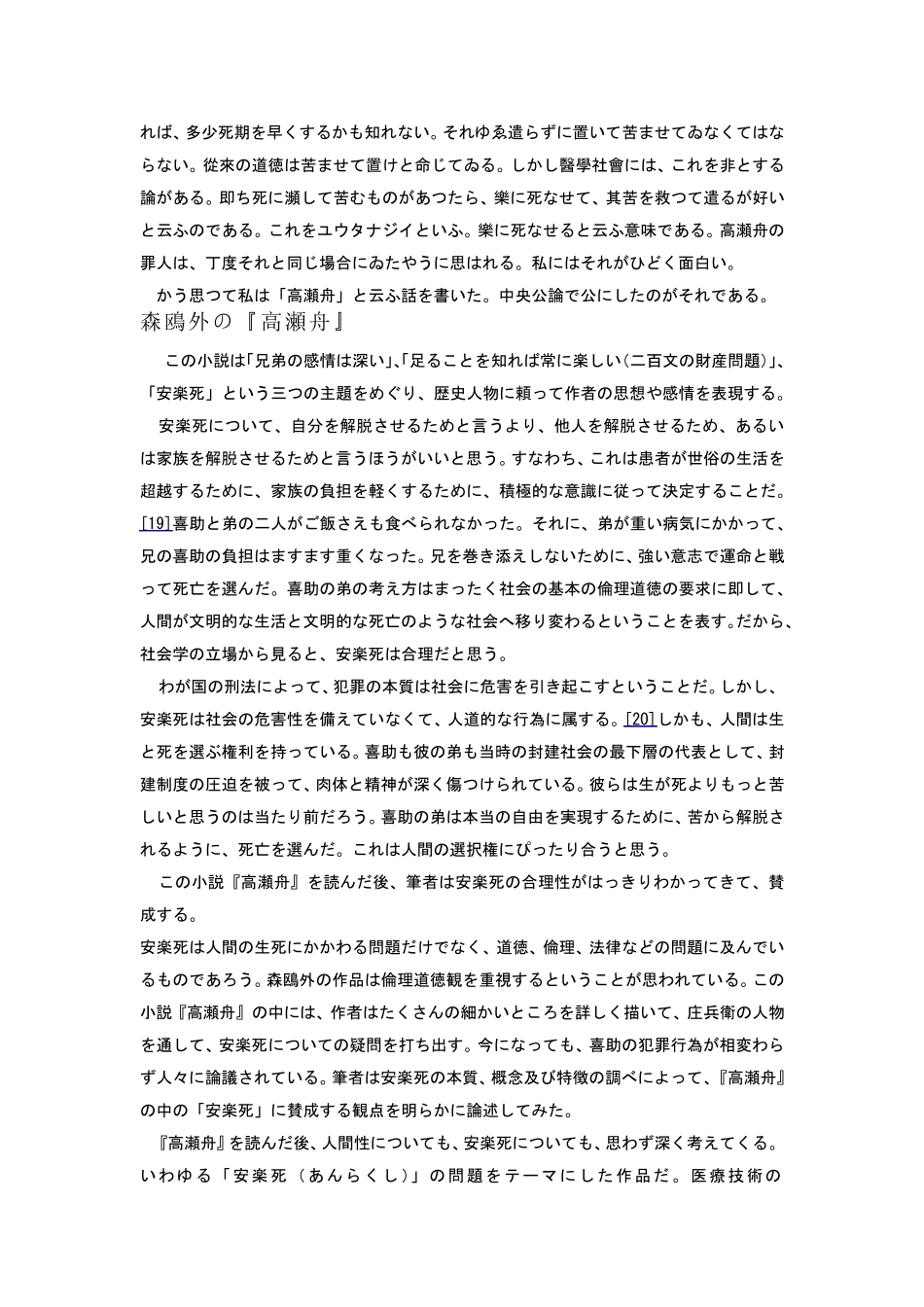『羅生門』 芥川龍之介 作者自身が「失業したら悪事を働くしかない」という下人の発想に近いものを持って描いたのではないかと私には感じられる。つまり、下人のような状況に置かれた場合は、誰もが「飢え死に」か「悪」かというような命題にぶつかり、誰もが下人のような悩み方をするものだというように、芥川は下人の迷いを一般化して捉えていたのではないかと思われる。芥川はここでの下人の迷いを下人に特有の個性を反映したものとしてではなく、人類の普遍的な命題として描こうとしているという印象を受ける。 周囲の事情というのは、つまり相手が簡単に盗みのできる老婆であること、周囲に人がおらず失敗する可能性がないこと、老婆自身が「悪事も仕方がない」と言っていることから、下人の盗みを老婆の理屈によって正当化できること、等々である。このような状況が少しでも変化すると(たとえば盗みが非常に困難な状況が生じるとか)「飢え死にしないためには悪事も仕方がない」という理屈はたちまち成り立たなくなる。しかし『羅生門』に描かれる小さな、閉鎖された世界には現実社会の要素が入り込む可能性はなく、状況が変化することはあり得ない。そういう意味で、「悪事も仕方がない」という下人の結論は、この世界においては必然的な流れになっていると同時に、この閉鎖された世界でしか成り立たない理屈であると思う。 「飢え死にしないためには盗人になるしかない」とか「飢え死にしないためだから悪事も仕方がない」という単純 な理屈は、現実社会の複 雑 な状況の中 ではたちまち維 持できなくなる。これを無 理に維 持させ ようとすれば、現実との妙 な衝 突 が生じるだろ う。この単純な理屈を成り立たせ なくするような現実の様 々な要素をすべ て排 除 した、小さな、特殊 な世界を描いたのが『羅生門』である。 高 瀬 舟 一つは財 産 と云 ふ ものの觀 念 である。錢 を持つたことのない人の錢 を持つた喜 は、錢 の多少には關 せ ない。人の欲 には限 がないから、錢 を持つて見 ると、いくらあればよいといふ限 界は見 出 されないのである。二 百 文 を財 産 として喜 ん だのが面 白 い。今 一つは死に掛 かつてゐ て死なれずに苦 ん でゐ る人を、死なせ て遣 ると云 ふ 事である。人を死なせ て遣 れば、即 ち殺 すと云 ふ ことになる。ど ん...